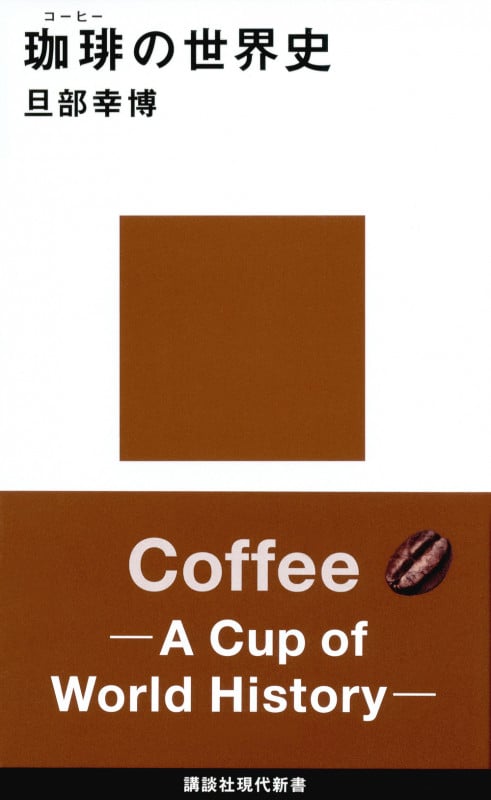『つゆのあとさき』
永井荷風
岩波文庫
カフェの日本史を調べていると必ず出てくる「純喫茶」ではない「カフェー」。和装に白いエプロンの女給さんというイメージは浮かぶものの、どういう店なのか、女給の仕事はどんなものなのか、風俗営業に近いこともあって具体的には書かれていないので気になっていました。
そこで女給を描いた小説を検索してみたら、真っ先に出てきたのがこちら。1931年(昭和6年)の作品。銀座のカフェーで女給として働く君江が主人公。
永井荷風は初めて読みましたが、解説によると「生涯の大部分を独身で過した荷風は、日本人離れした西欧的合理主義から、定期的な性的欲求を満すためにだけ、常に一定の女性と契約を結んでいた。」ということで、だいぶゲスな生活をしていたようです。
荷風が気に入って通っていたのはカフェー・タイガー。カフェー・パウリスタ、カフェー・ライオンと並んで、カフェの日本史には必ず出てくる名前で、「美人だが素行の悪さでライオンをクビになった女給がタイガーで雇われ、お色気路線の営業をしていた」そうです。
常連だっただけあってカフェー店内の雰囲気がわかりやすく書かれています。
女給は早番だと11時、遅番だと15時出勤。
食事を運んだり、お茶を入れるわけでもなく、客と同席するのが仕事。今のホステスに近い感じですかね。
客は女給目当てで通ってくる人もいれば、商談や買い物帰りで普通に喫茶として利用している人もいたり。
給料がどうなっているのかわかりませんが、基本的には客からもらうチップで稼いでいる。
カフェー自体は喫茶として営業しているわけですが、客と懇意になった女給は誘われれば仕事帰りに客とともに待合へ、というのがパターンのようです。
この「待合」も小説にはよく出てきますが、現存しないのでいまひとつ実体がよくわからないシステム。料理は近くの料亭から運ばせ、食事もできるけど、お風呂が沸いていたり、隣の部屋には布団が敷いてあったり、ほとんどラブホテル的な役割。
『つゆのあとさき』では神楽坂にある待合が出てきます。今でも神楽坂は細い路地の奥に知らない人はたどりつけないような料亭があったりして、色街の名残を感じます。
神楽坂だけでなく、カフェーのある銀座、君江が住んでいる市ヶ谷本村町、松陰神社など、通りや風景が細かく書かれているので、現在の地図と照らし合わせながら、当時を想像してみると楽しい。
主人公の君江は貧しい家に生まれたわけでもないのに、ただふらふらと私娼になり、そのまま女給になり、恋人がいても他の客に誘われるままに浮気する、自堕落な女として描かれています。
実際にカフェーの女給には君江のような女性もいたのでしょうが、荷風自身が恋愛を信じていないようなところがあり、女給を軽く見ている感じもします。
君江だけでなく、彼女のまわりの男性客に対しても一定の距離をおき、誰に対しても共感や同情もなく冷めた目で描いているのがこの小説の特徴でしょうか。
谷崎潤一郎はこの小説を「記念すべき世相史、風俗史」と評しています。特に事件も起こらず、昭和初期の風景を描いただけ、なんですが、それが時代のざわざわ感とともになぜだか心に残ります。
「数寄屋橋の朝日新聞社に広告の軽気球があがっている」という描写があり、あれ?と思ったら、当時は数寄屋橋に朝日新聞本社があり、その跡地に有楽町マリオンが建っているんですね。今はそのマリオンも西武や映画館が閉館してだいぶ変わりました。そういう変化していく風景の一場面を切り取ったような感じがあります。
(102ページ)
疑獄事件で収監される時まで幾年間、麴町の屋敷から抱車で通勤したその当時、毎日目にした銀座通と、震災後も日に日に変って行く今日の光景とを比較すると、唯夢のようだというより外はない。夢のようだというのは、今日の羅馬人が羅馬の古都を思うような深刻な心持をいうのではない。寄席の見物人が手品師の技術を見るのと同じような軽い賛称の意を寓するに過ぎない。西洋文明を模倣した都市の光景もここに至れば驚異の極、何となく一種の悲哀を催さしめる。