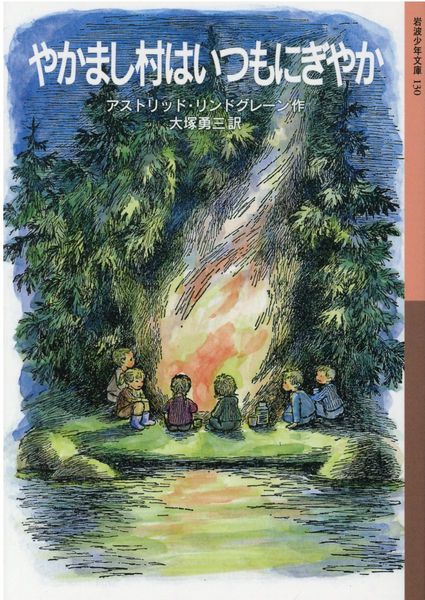『紙の月』
角田光代
角川春樹事務所
三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件が公表されたとき、『黒革の手帖』か『紙の月』かと思った人は多いはず。現実はそんなにドラマチックではなく、男に貢いでいた訳でもなく、FXの損失に充てていたとか。(とりあえずボブだから和久井映見似とかいうの失礼だよな。)
『紙の月』は実際に起こった事件をモデルにしたわけではなくフィクションですが、彼女が横領を繰り返していた1995年〜2000年あたりの時代背景がじつにリアル。とっくにバブルは崩壊しているけれど、ブランドはまだキラキラと存在していて、今よりずっと日本はお金持ちで、でも先行きは不透明で、足元はなんとなくふわふわとしていた時代。
宮益坂のビアホールとか、赤坂のホテルとか、二子玉川のテラス席のあるカフェとか、モデルがありそうな店の描写には懐かしさを感じるほど。
1億円を横領し、すごい勢いで使い込んでいく梨花も、梨花をめぐる元同級生や元彼たち、誰もお金で幸せになっていないのが辛い。むしろお金を使えば使うほど、本当は何が欲しいのかわからなくなっていく感じが怖い。
今となってはブランド品を買い込んだり、ホテルのスウィートルームで過ごしても、幸福感は感じないんじゃないかなと思う。お金で買える幸せがあるかのように錯覚できた時代。